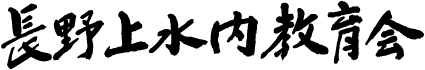この記事にいきなり来てしまった方は、直前の「新版データベース・・・って何なの?」もご覧ください。
さて、この記事では「新版」の能力をお試しいただきますが、「データベースの使い方案内(練習?)」にもなりますから、ちょっと試してみませんか?
★長い記事ですからお時間のあるときにでも。
まず、お手元に配布済みのパスワードをご準備ください。データベースに入るときに必要です。(お忘れの方は各校代議員の先生にお尋ねください)
それでは、画面左上隅の「長野上水内教育会」のボタンを右クリックして「新しいタグで開く」を選びます。新しいタグの方で「教材データベース」(画面一番下にボタン)を開いたら準備完了!
これで、このブログとデータベースを行ったり来たりできます。
さぁ、始めましょう。
◆◆まず、忙しい先生向け(笑) 最速で核心に迫る方法◆◆
能率的なのは「キーワード検索」で、「水産業」で探すと9件ヒットします。
やはり、この方法は的確です。 ・・・でも、「適切なキーワード」を知らないと意外に使えないってところが泣き所です。(笑)
それから、キーワード検索は「キーワードしか見えてない」ってことでもあります。世の中には「寄り道の楽しみ」ってこともありますよね。そこは忘れないようにしたいところです。
◆◆そこで、手探りで探す場合・・・とりあえず2種類◆◆
「分類から探そう」で「産業」→「水産業」では7件をとらえることができます。ちなみに、「サケ(鮭)」の語もタイトルにちらほら見えるはずですから、あらためて「サケ」で検索するワザもあります(今回は略)。
もちろんこれは王道ですが、それだけではこのブログの意味がありません。(笑)
それに、「7件」って数字を見ていただきたかったから、最初にお試しいただきました。そう、「チト足りない・・・」ですね。不足分はあとで説明しますから、もうひとつの「手探り」をやってみましょう。
ここからが本題です。「単元から探そう」ボタンで「食料をつくる」を選ぶと134件ヒットしますので、地区で絞ってみましょう。仮にご自分が「若穂」の学校にお勤めだとしてコレを選ぶと、酒蔵なども含めた14件が残ります。もちろん「東勝寺の湧水」も出ています。
ひと文字も入力せず、「水産業」なんて単語も使わなかったけれど、けっこう面白いものが出てきたと思いませんか?
ただ、疑問もあります。そう、どちらの方法でも、キーワード「水産業」でヒットした野尻湖・霊仙寺湖には到達できませんでした。
ですが、これは故障ではなく「仕様」です。このあたりが「上級への早道」ですので、もう少し掘り下げましょう。
◆◆野尻湖を例に探る本データベースの挙動やねらい◆◆
「野尻湖」は分類では「水産業」ではなく「自然>湖・沼・池」に入っています。つまり「水産業」という引き出しの中に、「野尻湖」は収納されていないのです。
でも、ご存じの通り、冬の野尻湖の風物詩「穴釣り」はレジャーであり「水産業」です。そこで、ユーザーから見えない場所にキーワードとして「水産業」や「サービス業」を設定してあります。それでキーワード検索だとヒットするというわけです。(霊仙寺湖も同様)
では、キーワードを使いこなさなければ、「水産業の舞台としての野尻湖」を発見できないのでしょうか?
そんなことはありません!・・・というのが「新版」の真骨頂です。
新装の「単元から探そう」ボタンで「商業・サービス業」を選び、地図から信濃町に絞り込んでみましょう。野尻湖が出てきましたね。システムが「レジャー産業」として引っかけているからです。
しつこいですが、もうひとつ。「単元から探そう」ボタンで「食料をつくる」を選びます。ここまでは、さっき試しましたが、今回は地図から「信濃町」に絞り込んでみましょう。出ましたね。
このように、「野尻湖」の写真には、分類の「自然」だけでなく、産業としての「レジャー」と「水産業」の2面、合計3ルートからたどり着くことができるわけです。
適切なキーワード検索はやはり効果的ですが、新装の「単元から探そう」ボタンの効果も感じていただけたのではないでしょうか。
今回実装された「単元から探そう」ボタンや、新たな「分類」設定は、当初は容易に情報に迫れるようにすること(アクセシビリティの向上)が目的でした。しかし、結果から見ると二途三途の考え方で情報を洗い出す能力(データベースの本質的パワー)も大きく向上させたと考えます。
「野尻湖」の性格の一つに漁業があることを知らなかった児童生徒が、このデータベースで調査することを通じて、次第に視野が広がっていく・・・そんな学習のツールになることが私たちの(遙かな)目標です。
さて、話のスタート地点に戻ります。
「東勝寺の湧水」(このブログの写真)は、ひとまず「産業>水産業>生産施設」の引き出しに収納されているデータです。ですが、もちろん「泉」「産業の遺跡」「庭園の遺跡」「寺院」など様々な性格をもっているので、たとえば単元ボタンの「郷土の歴史と大切なもの」からでもたどり着けるようになりました。これが「新版」の良さだというわけです。
もちろん、完全なシステムにはほど遠く、来年度も大改訂が必要なのですが、一歩ずつ良いものにしたいと思います。使って感じた不便な点など、ぜひご意見としてお寄せください。

サケの孵化に使われたと見られる池の中央部。庭園の遺構も残り、歴史の重なりを感じる。
◆◆アウトソーシングですが、地図も使えます!◆◆
最後に、綿内村の説明(前の記事)で使った「明治時代の地図」と現地を見比べる方法です。「教材データベース」左側ボタンの一番下にある「リンク集」を開きますと、国土地理院系のボタンのすぐ下に、県立歴史館系のボタンがあり、「絵図・地図アーカイブ」を開いていただけば簡単に明治の地図に到達できます。地図が残っていない町村が数%ありますが、これは全県700町村(明治12年現在の町村数)に対する割合ですので、まずは試してみてください。現在の「大字」にあたる町村を9割以上の確率で発見できるはずです。
むろん、現況地図の方は「地理院地図」が最適です。これとGoogleマップの3点を併用すれば、とりあえず歴史地理的な地域の情報を探っていく出発点になると思います(社会科/総合的な学習 ほか)。このあたりの便利なサイトも是非お試しください。
さて、長時間ありがとうございました。
これだけできれば、縦横無尽にデータベースを渡り歩けます。ぜひ、新年度にご活用ください。
教材データベース委員会