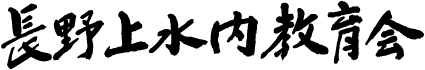◆チャットに書き込んで頂いた内容も含めて、「教育対話」に関わっての感想、ご意見を紹介します。(一部抜粋)
・ 貴重な時間でした。語り合った中身が、方法論でないところがよいと思いました。願い、思い、こうしたことは、対話しなければ、見えてこないと思います。また、武田先生、岩川先生の的確な助言にも研修が深まりました。
・ パネリストの先生方の言葉はもちろんですが、岩川先生のお話に感銘を受ける場面がとても多かったです。子どもたちとの学校生活を、もっと楽しんでいこうと思いました。
・ 子どもができたか聞いてきた時が対話のチャンスである。ここが特に印象に残っています。これまで、できた・できていないの評価を子どもに押し付けていました。子どもが本当に聞きたかったのは教師の判断ではなくそこからの自分のことをもっと知ってねという声だったのかもしれません。
・ 知らず知らずのうちに失敗できない「圧」が教育現場にはあるのだと感じました。自立する教師を考えていきたいと感じています。
・ 失敗は大人がつくる尺度、子どもにとっては育ちのプロセスの一部などのお話しから、これまでの当たり前や無意識に持ち続けてきた意識や感覚を問い直す時間になりました。本当に楽しく学べる時間でした。
・岩川先生の「自律は、森にたつ木であって、机の上にたてた鉛筆ではない」という言葉がとても心に残りました。子どもたちのことをしっかりと支えるために、教師自身が支え合っていくことが大切だと思います。
・ 自立と孤立が全く異なるということを改めて感じました。多くの人と関わり合うことが、最終的に本当の自立繋がることになるのだということを実感し、今後の教育活動に生かしたいと感じました。
・ 3人のパネリストの先生方の、日頃の授業実践や児童生徒との関わりに関するお話を興味深くお聞きしました。探求の学びを子どもに渡す・委ねるときに、教師自身の子どもとの関係が変わっていくという岩川先生の言葉が印象に残りました。一斉指導とは異なる仕方で、子どもたちとの関係を作っていく時代になっていると感じました。
・ 岩川先生、武田先生、パネラーの先生方のお話や、チャットのコメントを見ながら、一つ一つ頷いたり、どうかな、と考えることの連続でした。「依存できるのが自立」、「互いにケアし合える教室、そして職場。」新たな視点を与えていただく場となりました。
・ 本日は、自律した学習者を育成することのヒントをいただきました。自律そのものの捉えがぼやっとしたままでいた自分がいました。目の前の子どもを生涯学習者としてみた時、「自律した」というよりも、自律していく学習者を育成する意識でいたいと感じています。
・ 自律は十分な依存があってこそ、そしてそのためには失敗という概念や知らず知らずのうちに各々が持ち備えている他者をカテゴライズするものさしを取り払うこと、子どもだけでなく教師自身も本当の自律に向けて変貌し続けていけることをお聞きして、とても勇気をいただきました。日頃ぼんやりと思っていたことが、こういうことなのかと言語化され明確化されたように思いました。
・ 自律した学習者を育てるためには、教師自身が自分の弱さに向き合い、周囲にさらけ出すことが大事であると感じた。そんな姿勢が子どもたちに伝わり、本音を語れる自分、仲間の姿に共感できる自分を再認識できる。そのことが子ども同士のつながり、教師と子どものつながりを深め、広めていくことにつながっていくように感じる。
・ はっと日々の自分を反省することが多々ありました。スペックを効率よく教えようとしていた自分の授業…。子どもに正解を求め、圧をかけていた自分の関わり…。今日、はっと気づけたことを良いことだと思い、月曜日からの子どもたちと過ごす時間を考え直したいと思います。
・私も悩んでいることを先輩に申し訳なくて相談できずにいた部分があったので、少しずつ周りに相談して自分も大切にしていきたいです。そして、自分だけでなく、周りの先生のお話を聞き、雑談の中にも教育の糸口があるかもしれないため、大切にしていきたいです。
・ パネリストの皆さんが、ご自身のご経験から語られる言葉にいろいろ考えさせれました。岩川先生が最後におっしゃっていたように「立場は違っても、同じ教育に携わる者として対等である」という同僚性を大切にしたいと思いました。「依存するには勇気がいる」「依存の仕方がわからない」、子どもだけでなく、自分もそうかもしれません。
・ かしこまった話題、対話で終わるのかと思っていましたが、まさにファシリテーター、パネラーの先生方が、岩川先生のおっしゃる「対等、平等だと思えば、自分の言葉で語ることができる。」をライブで体現いただき、対話の有効性についてリアルにお示しいただき、聴いているだけでも学ぶことが多かったと思います。
・ 武田先生のファシリテートで様々な切り口での話が展開され、自分事として考える時間となりました。子どもも大人も、コミュニティの中で生まれるかかわりから自分が何をすればよいか、何をしたいかが見えるのだと実感しています。何か一つでも、小さなことでも、日々の営みの中から、何か違うのではないかを考えて行動していきたいと思いました。
・ パネリストの先生方の実践に裏付けられたご発言はどれも心に響きました。 新しいことに取り組む時、誰しも不安はありますが、失敗したっていい!という雰囲気が職場にあるかないかはとても大きなことだと感じました。3人の先生方のお話には、先生方と不安を乗り越えながら自律した学習者の育成を実践していくためのヒントがたくさんありました。
【当日、チャットに書き込んでいただいた感想、ご意見】
・自立するためには、たっぷりと他者に依存することが必要であることは、学習院大学佐藤学教授も述べていました。家庭環境の変化により、生育の中で十分に依存できなかったことがなかなか自立できないことにつながっているのではと感じました。学校の中では、依存と甘えの境目が難しいと感じます。
・まずは、自分をさらけ出すこと、そして人は誰かに受け入れれて誰もが居場所ができるのではないでしょうか。皆さんいかがでしょうか。
・私は自律できていないです。だからいつも「できません」と言ってしまいます。すると周りの先生もですが、すぐに助けてくれます。職員室で叫んでいます。子どもにもできないと演技します。みんないい人なので助けてくれます。これが支えになり、また自分も支えたいという気持ちになります。そんな職場やクラスを作っていきたいなあ。いま、安心して先生方の話を聞いています。
・若い先生ほど「できない」「わからない」と言えない雰囲気を感じます。だからこそ、50代に差しかかった自分が「できない」と率先して話しています。自分をさらけ出すこと、助けてということが苦手な子どもたち、先生たちは、どうしたら自己開示ができるようになるのでしょうか。
・教師の自立・自律を阻むもの「昔はよかった」とよく聞きます。色々チャレンジできる環境であったり、バイタリティあふれる先輩が多かった。失敗してなんぼ。現在はSNS、厳しい目、教師としての責任といった様々な圧の中、自立・自律を阻んでいるような気がします。でもいつも助けてくれるのは、その時その時の職員室と家族でした。今もいっぱい助けてもらっています。
・武田先生がおっしゃっているように、教師も子どももうまくやらなきゃいけない、という空気はあるように思います。失敗しそうでも、とりあえずやってみよう!という空気が学校現場にもっと出てくるのが大事ではと思います。
・子どもも学んで自律していっていることを考えると、教師もいろんな先生や学べる教育会のような場所を使って学んでいくことが大切なんだろうなあと感じました。Edカフェの先生方ありがとうございました。
・自分のものさしで自分自身が前に進めずにいると感じました。今までやってきたことを変えることが怖く、失敗を恐れています。こうじゃなきゃいけないと思うことをこわして、先生方と子どもたちのことを語っていけたらとおもいました。