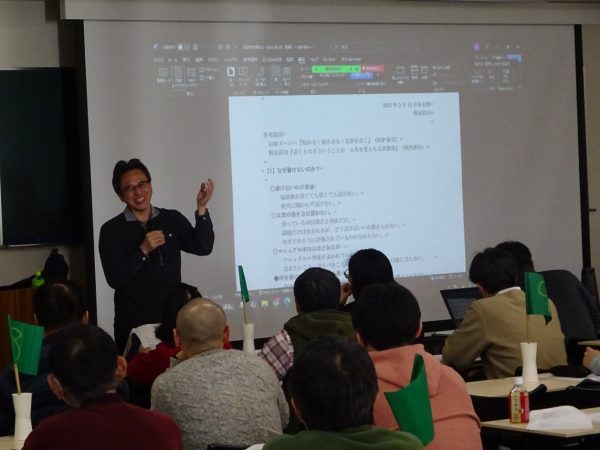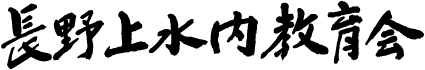2月15日(土)に、東京大学大学院総合文化研究科教授・梶谷真司先生を招いて、『哲学対話~対話的文章法の試み~』を、信州大学教育学部大講義室にて行いました。今回は、グループで一緒に問い語り合うことで文章が自然に書けるようになる『対話的文章法』を体験しました。参集とオンラインのハイブリッド方式で実施し、130名を超える10代から80代までの異なる年齢、異なる職種や立場の皆様にご参加いただきました。以下に感想を紹介します。
〇今まで文章の書き方を学ぶ機会がなかったのでとてもためになりました。子どもたちが「書けない」という理由が、梶谷先生のお話から「そうか、だから書けないのか」と分かりました。反対に、卒業文集制作では無意識に自分が子どもたちに問いを投げかける機会が多く、それが自然と対話的文章法に近いものになっていたのかもしれないと思いました。どう考えるのか、何を考えるのか、どんな視点が必要なのか、自分の持っている材料は何なのか、そういうものを整理していくことが大事だと思いました。
〇文章を書くときにいつも時間がかかり文章を書くことに苦手意識がありましたが、これまでの自分は格好のいい見栄えのする文章を書こうとしていたから、つまずいていたのだと気付くことができました。自分なりの言葉で書くこと、考える前に書き出してみること、ストラクチャーをブラッシュアップすること、文章を書く上で大切なことをたくさん学ぶことができました。
〇本当に文章が書けるようになるのかな、と思って参加しましたが、活動を通して少し書けるようになったなと実感することができました。普段何気なく書いていた文章もどんなポイントを持って書けばいいのかということが分かりやすかったです。
〇文章を書くということが、平面的でなくて立体的に見えてきたように感じました。考えてから書くのではなく、書いてから考える、手と目で考える、部品や材料を集めて組み立てる…少しワクワクするような気持になりました。もっと早くお話をお聞きする機会があったら、子どもに文章を書くことを強いるような指導はなかったかも知れない…と反省しました。
〇自分だけで考えるよりは、考えが広がり深まること、つまり対話を通して深い学びになることを学ばせていただきました。
〇年代が違う人達が集まり対話することで、見方、考え方が広がるのでとても楽しかったです。一人で文章を書く時、いつもストラクチャーを頭の中で何十回も作り直しながらやります。改めて、大事だなと思いました。
〇問いを回すことで「そうか、ここの部分はもっと説明しないとわかってもらえないんだ」ということがわかったり、予想外の部分に問いが集中して「なるほど、聞き手はそこに興味を持つのか」とわかったり、この演習はそのままスピーチに応用できると思いました。 ぜひ来年度の授業に取り入れたいと思います。 それ以上に、グループのみなさんのお話が楽しくて、とてもいい時間を過ごせました。 世代が違う方とこうやってフラットにお互いの話をする機会はなかなかなく、貴重なひとときでした。