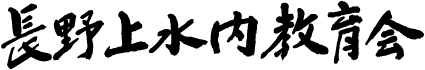11月23日(水)「第2回共育塾」が行われました。信州大学の佐藤和紀先生のご講演をお聞きした後、5つの実践者から学ぶ講座(ブレイクアウトルーム)に分かれ、普段悩んでいることやもっと知りたいことなど多くのことを発表された先生方から学ぶことができました。
◆ 全体講座 「ICTを当たり前に活用した個別最適な学びと協働的な学びの一体的な充実」
佐藤 和紀 先生(信州大学教育学部附属次世代型学び研究開発センター)
<〇:参加者の感想>
〇「個性化」頭の中にモヤモヤとあったものを言語化していただいて、「なるほど」と思いました。主体性の根源は選択できることだと思っていましたが、それにはこちらの準備がいろいろと必要で、大変なのでは?という感は、いまだに否めないのです。課題も多く見え、有意義な時間を頂きました。
〇これからさらに主体的な授業を行っていく中で、子どもたちが忙しい授業を考えていかなければならないと思いました。選択するという場面を多く設定し、ICTの活用もまずは自分がこなせるようになり、積極的に活用していこうと思います。
◆ 分科会講座
A:「自ら学ぶための足場をつくる自主自学の時間」 北原 大介 先生(須坂市立東中)
〇学校での「単元内自由進度学習」では、学習効率の高まりがあり、その子その子のペースで学習ができていてすばらしいと思った。そのためには、教師側があらかじめ準備をしっかりしておくこと、授業でつけたい力は何か、しっかり把握しておくことが大切だと感じた。
B:「理科の自由進度学習を通して、指導の在り方を考える」 成田 剛真 先生(市立長野中)
〇素晴らしい実践をもとに、主体的な子どもたちに育てるための「教師の在り方」を教えていただきました。挑戦する意欲の高さが素晴らしいと思いました。成田先生の姿を見て、私も自分なりにできる挑戦を考えたいと思いました。
C:「読み書き困難な児童への支援」 東田 幸恵 先生(鍋屋田小)
〇東田先生の発表は、実際の通級での指導の様子が具体的に伝わりました。実際利用されている教具や教材、アプリなど、すぐに参考にしたい内容が盛りだくさんでした。その上で、目の前の生徒にどうアプローチしていけばよいか、もちろんひとりひとり異なるのですが、何か、ヒントを頂けたような気がします。
D:「ICTる?」 伊藤 真紀 先生(信濃小中)
〇信濃町小中学校さんの取り組みから、多くの学びを得ることができました。特に、伊藤先生の授業実践からは、子どもたちが自ら学習計画を立てるということのよさを学ぶことができました。「こんなことが4年生でもできるのか...」と驚かされました。同時に、教員として自分自身がもっとICTに触れる機会を設けていく必要があるなと実感しました。
E:「多角的な視点による子ども理解について」 小林 聖明 先生(裾花小)
〇試行錯誤を繰り返しながら、よりよい教科担任制の在り方を追求している裾花小学校の取組を聞かせていただき、やる気と勇気をいただく時間となりました。本校でも、来年度から本格的に取り組んでいこうと考えていますので、これまでの実践でつかんできたノウハウを活用させていただきます。
休日にもかかわらず参加して下さった講師の佐藤先生、実践発表者の先生方、参加者の先生方ありがとうございました。来年も先生方の声に耳を傾け、共育塾で主体的に学んだ先生方が、「学びの主体を子どもたちに」つなぐ企画を考え、共に学ぶことができればと考えています。
(塾企画運営委員会)