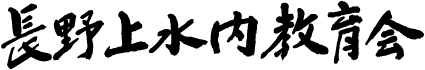12月22日、柳原小学校を会場に、信濃教育会会長 武田育夫先生を講師にお招きし、道徳教育について研修会を行いました。
まず、3人一組になり、「信号のある交差点。しかし夜遅く、車は来ない。安全である。赤信号の時渡るか、渡らないか。」考えることをしました。渡らないというのは交通ルールを守るため、渡るというのは信号という機械に支配されるのは嫌など、武田先生から根拠の例を示していただいた後、自分の考えや理由を3人で出し合い、話し合いをしました。一人が進行役を務めます。そのあと、進行役以外の二人は、席を移動して最初とは違うメンバーと3人組を作ります。進行役だった人がどのような話し合いがなされたかを、あとから来た二人に紹介し、その後3人で考えを出し合いました。話し合いの後、武田先生は、「これを通して、自分の中でどのようなことが起こっていましたか」と問われました。自分の中で起こっていたことを何人かの先生が話されました。私自身、自分は何を基準に、どんな価値観をもって生きているのか自己を見つめることをしていたように感じました。ワールドカフェのやり方であると教えていただきました。
次に、小グループで、日頃の道徳の実践や悩みを出し合いました。「授業の終末をどうすればよいか」という質問が全体の場に出されました。それについての意見交換がなされ、武田先生からもご示唆をいただきました。人として、教えなくてはいけないことはあるが、一つの価値に導くことについての問題が投げかけられました。道徳は、自分の心が揺れる、自分はどういう思いでいるのか、どうすればいいのか考えること、いろいろな考えや価値観に触れられることが道徳の時間で大事であることを改めて感じました。資料についても、子どもに何を考えさせようかと思いを巡らせながら授業を考えていくことを教えていただき、子どもと道徳の授業をすることのわくわく感が増してきました。道徳って楽しい、やってみたい、子どもの素敵な時間を共有したい、そんな思いをもてた時間でした。
参加した先生の感想も載せます。
〇武田先生との会に初めて参加させていただきました。武田先生の懐の深さと軽快な語り口に、楽しく気軽に話すことができました。今まで道徳の授業を考えるときに「どんな発問をしようか…」「教材の補足説明が必要かも…」と、ねらいに迫る手立てについて教師の手を加えることを考えていました。しかし今回の武田先生のお話を聞いて、子どもの心の揺れとそこから生まれる子ども同士の対話の大切さに気づき、手を加えることだけでなく「どこで引くか」についても考えていかなければならないと感じました。
終わりから始まる道徳* の学習?
〇昨年に引き続き武田育夫先生と『道徳教育を語る会』に参加させていただきました。ワールドカフェ方式で、ある状況について、「あーだ、こーだ。自分はこういう感じ方をする、もしこうだったら迷わずこうするんだろうなあ、だってね‥。」と話した後、グループを入れ替えて、また対話するという時間を過ごしました。いろいろな人のメモに目を通し、自分の考えたことを書き込みながら、自分は、「功利主義者か?」などと、うっすら感じる場面もありました。堅苦しく身構えるわけでもなく、「自分と向き合う、自分を見つめる」などと表現されることって、こういうことなのかもしれないな、主体的、対話的な学びってこういうことかもしれないなと考えさせられました。会が終わったあと、自動車を運転しながら、「今、自分は、功利的に考えているなあ」「あの時、こう考えている人がいたなあ」等と、思いを巡らせていました。以前聞いたことのある『終わりから始まる道徳』が今回の体験なのかもしれないと思いました。
*『終わりから始まる道徳の学習』信州大学教育学部 高柳充利先生 演題より
〇毎年12月の忙しい時期に開催されますので,今年はどうしようかと迷いながら申し込んでいます。それでも今まで皆勤状態を続けているのは,会に行けば必ず行ってよかったと強く思える何かを持って帰っているからです。今年度は「赤信号渡らない・渡る」という内容で,ワールドカフェ方式(初めて知りました)で行いました。武田先生は途中で「中心発問はない」「『〜について話し合いましょう』という言葉だけで始めた」と種明かしのように話していましたが,それでとても楽しい話し合いになり,普段考えていなかったことまで実感できる内容になったので,自分の授業のとらえ方について考え直さずにはいられませんでした。授業のまとめについての考え方や,上皿天秤の話などおもしろい話はいくつもありましたが,個人的に今回すごく刺激を受けたのは,「手品師」の話でした。六学年で二学期に取り扱った内容だったからです。何となく出来たつもりになっていた授業でしたが,もう一回取り扱ってみたいという欲求が出てきました。武田先生の話は難しいものではなく「今度,自分でもやってみたい」と思わせるものが多いのです。
〇今回は「意見交換の場」もとても充実していました。「Dの領域の扱いの難しさ」「話し合って深めていく場面での特別支援学級の子どもたちの辛さ」「学習指導案を使う授業の是非」など,自分が普段から感じている悩みやあまり意識していなかったことに目を向けさせてもらえることの話の数々は,もう少し話していたいと思わせるものでした。特に最近は,日頃の授業改善の中で,道徳の授業での中心発問と子どもたちの反応にズレを感じるという場面が何度かありましたので,指導案の取り扱いについての話題は目から鱗が落ちるような思いになりました。最後に武田先生から話していた内容についていくつかヒントがもらえるという贅沢さで,会の終了時に初めて話す会員の先生と「楽しかったですね。」と言い合えたのも嬉しい一場面でした。来年も,忙しいからどうしようと迷いながら結局出席するような気がしています。
もし、道徳についてもっと研鑽を積みたい、悩んでいるという先生は仲間になりましょう。無理なく楽しく研修します。
(文責 牟礼小学校 松谷かおる)