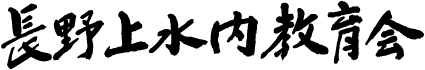11月1日、筑北村の聖南中学校を会場にして、道徳学会県大会が開催されました。聖南中学校では、35時間のうち13時間ほど全校道徳に取り組んでおり、今回も全校道徳の授業を公開していただきました。全校道徳は、1年から3年生の生徒を縦割り班にして行い、1つの班7~8名ほどで構成されます。これにより、学年を越えて多様な意見に触れ、個々の見方考え方の深まりや広がりにつながっているそうです。また、授業も、授業者から発問するだけでなく、生徒の課題意識から問いを設定する授業、問題解決的な道徳の授業に挑戦されていました。全校道徳の際、班が9班ありますので、9人が授業者となります。ですから、授業構想について、先生方が自主的に学び合うこともしているそうです。縦割り班で話し合った後、ロイロノートに自分の考えを載せることもしており、ICTの活用により班の中にとどまらず、いろいろな人の意見に触れることもできました。
11月1日、筑北村の聖南中学校を会場にして、道徳学会県大会が開催されました。聖南中学校では、35時間のうち13時間ほど全校道徳に取り組んでおり、今回も全校道徳の授業を公開していただきました。全校道徳は、1年から3年生の生徒を縦割り班にして行い、1つの班7~8名ほどで構成されます。これにより、学年を越えて多様な意見に触れ、個々の見方考え方の深まりや広がりにつながっているそうです。また、授業も、授業者から発問するだけでなく、生徒の課題意識から問いを設定する授業、問題解決的な道徳の授業に挑戦されていました。全校道徳の際、班が9班ありますので、9人が授業者となります。ですから、授業構想について、先生方が自主的に学び合うこともしているそうです。縦割り班で話し合った後、ロイロノートに自分の考えを載せることもしており、ICTの活用により班の中にとどまらず、いろいろな人の意見に触れることもできました。
午後は、4つの分科会に分かれ、それぞれの分科会では2支部から出されたレポートをもとに、日頃の自分の授業や道徳について気軽に語り合いました。長野上水内からは豊野西小学校の本間大貴先生がレポート発表をしていただき学び合いました。子どもの発言をどうとらえていくか、発言の背景にあるものは何か、子どもの内面にまで思いをはせながら、評価や子ども理解について参加者で意見交流をしました。
講演会では、帝京大学教育学部初等教育学科教授(元文部科学省調査官) 赤堀博行先生より「道徳教育のマネジメント」という演題でご講演いただきました。学校における道徳教育の全体像をお話ししていただいた後、道徳科の目標に基づく授業づくりについて具体的にわかりやすく教えていただきました。授業をする上では明確な指導観(価値観・児童生徒観・教材観)をもつことが大事で、その具体を実際の資料をもとに話されました。ご講演の中から、授業づくりについてすぐに実践に活かせそうな点を2つ紹介です。1つは、どこに中心発問をもってくるか。それは資料の山場でなく、授業者がその時間1番子どもに考えさせたいところであり、授業づくりは中心になるところから作っていくこと、2つ目は、安易な「なぜ、どうして」の発問はやめようということです。よく、「どうして」という問いを発してしまいますが、それは理由や背景を問うことで、道徳の授業で考えさせることは、「道徳的心情」または「道徳的判断力」であるため、問う対象は「感じ方」「考え方」だそうです。
道徳について学びたい、関心がある仲間と授業参観や、それぞれの実践を通して語り合い、赤堀先生から授業づくりの具体を学ぶことができた、有意義な1日でした。