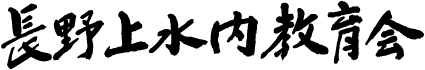道徳教育学会 県大会報告
11月2日(木)長野県道徳教育学会が山ノ内町立西小学校を会場に行われました。長野上水内道徳教育学会からは5名参加しました。山ノ内町の小中学校はユネスコスクールに認定されていて、各校ESD(持続可能な開発のための教育)に取り組んでいます。有名なのはABMORI(市川海老蔵さん、今は団十郎さん)が志賀高原に植樹をするという活動を何年も続けられ、今年も5000本以上の植樹をしたそうです。
今回の授業は、6年生の「海のゆりかご―アマモの再生―」の資料を用い、アマモの再生の取り組みについての新聞記事を読んだ主人公の思いを考えながら、自分たちが関わっていることと関連付けながら、自然を大切にする意義について考える授業でした。資料を読んで、子どもたちが感想や疑問を出し合うことから、考えることを焦点化していく授業を積み重ねられていること、体験を道徳の授業に生かすことが参考になりました。また、自分の考えをまとめる際、自由に友だちの所に行き、互いの考えを見合ったり、また、考えがまとまらないときは友だちの考えを参考にしたりできる学び方がありました。指導主事の先生から、道徳の授業で大事にしたいこととして、①問題意識をもつ②自分との関わりで考える③多角的多面的に考える④自分を振り返る⑤自己の生き方について考えを深める を挙げられました。
午後は4つの分科会に分かれ、A41枚、半分は授業の板書、もう半分は授業の振り返りを書いたレポート2本をもとに気軽に語り合う時間でした。長野上水内からは柳原小学校の宮澤和幸先生がレポート発表していただきました。協議の中で、道徳の授業でもICTを効果的に使うことについて話が出ましたが、効果的である部分と、ICTに頼りすぎないでことばで語ることの大切さが出されました。このほか、価値理解を図るためには、道徳的価値についての大事さはわかっているけれど、なかなかできないこともあることについて安心して目を向け語られること、友だちとの意見交流の大切さ、先生も子どもと一緒に考え、時には子どもの考えに教えられることもある等、授業をしていく上で大事にしたいことがそれぞれから語られました。最後は道徳のアシスト6の題名にある「そう、道徳は楽しい」と感じられた実践を出し合いました。明日から、また、子どもと楽しく道徳の授業をしたいなという気持ちが膨らんだ時間でした。
講演会は、信州大学教育学部教職大学院教授 畔上一康先生から「その正義は誰のものか~議論から対話へ~」という演題で行われました。道徳の授業を行うとき、1時間のねらいを決め、授業に臨みます。しかし、ねらい達成に至らないと思うこともあります。個々の子どもで見ていくと、「この子はねらうところまで考えた、この子はまだ考えが深まっていない」と評価することがあると思います。「道徳で、こうすることがいいんだ、こうすべきだ。」などといった一見正義と思えることについて、その正義は誰にとっての正義なのか、子どもの考えに対して、あやまりと思える考えにも意味と背景はある、正義を振りかざす授業になっていないかと、私たちに警鐘を投げかけられたと思いました。人は自分の文脈の中で学ぶ、このことは畔上先生の教育の根底にあるものです。一見あやまりと思えることも、子どもから見れば正解かも知れません。私たちは、子どもの考えを、その背景から意味世界として見ることが大切であると話されていました。また、畔上先生は対話の重要性を話されました。対話を通して、相互に納得できる方法を探ることができるので、傾聴すること(対等の関係で話を聞くこと)が大事であるとも語られていました。「主体の自由性が外の権威にすりかえられてはならない」、「この子がこの子としていることのできる学校を」というお言葉から、私たちは道徳の授業、それにとどまらず、子どもの内なる声をしっかり聞いていくことがいかに大事か、改めて考えさせられた時間でした。「一人一人の声、それぞれに価値がある」「一人一人の今があり、明日がある」と締めくくられました。(文責:牟礼小学校 松谷かおる)