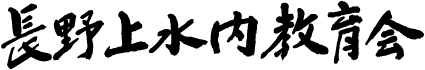浅川小学校の臼田瑞希と申します。今回は、6月26日に開催された長野上水内道徳学会発足の会において、会員の先生方の発言についてご紹介するとともに、そこで話題になった「対話」について、私自身が考えていることについてお話します。
〇道徳の教材は、年齢学年関係なく、いつ触れてもその時の感じ方や気づきを通して深めていくことができると改めて感じた。ある中学校にて、小学校1年の教材を扱った際に、中学生一人一人がその生徒なりに考えて、「う~ん」と迷いながら終えた。小学生の時に一度扱った教材であっても、成長した今の感じ方で再び迷いながら考えることには価値があると実感した。(豊野中 後藤真道先生)
〇「親切」について考えた授業の後半で、「このクラスにも、親切なことってなかったかな」と先生が問いかけ、ある子が「Aさんが登山の時に助けてくれて…」と発言があったとき、このAさんの顔が本当に印象的だった。日頃ちょっとツッパっていたAさんが、クラスメイトから「すごいじゃんか」と認められて照れくさそうにしていた。こういう行為っていいなって思った生徒たちが、教材の場面と身近な姿や場面を結び付けたとき、その喜びを共有する教室の雰囲気はすてきだなと思った。(牟礼小 松谷かおる先生)
〇ある教材を分割して、最後の場面を伏せて授業をしたことがあった。子供たちに「自分ならこの後どうする?」と考えさせた後に後半の場面を見せた。すると、「ああ、結局そうなんだ」と、子供たちはまるで正解を見せられてしまったように白けて、何とも後味が悪い授業になってしまった。それからまたこの教材を扱う機会があったときには、今度は最後の場面は伏せたままで終えたところ、子供たちは互いの考えを尊重しながら対話を深め、自分の納得解を心に残して終えることができた。(柳原小 宮澤和幸先生)
〇これまで授業を重ねていて、自分の広げ方や深め方には限界を感じることがあり、毎年数回、他県の授業を視察に行かせていただいてきた。実際に他県で行っている授業を見ると、「ああ、こんな進め方もあるのか」と、長野県のスタンダードなものと深め方が異なるのだなと、様々な方法を学ぶことができて、自分の授業でも真似してみたくなるので、また機会をいただいて参観したいと思っている。(朝陽小 天野真先生)
〇自分の今後の課題としてご指導いただいたことから、日常生活において、子供たちはいつでもどこかでこだわる姿を見せる。その姿こそ個性で、そのこだわりを共有していくことから対話は生まれてくるのだろうなと感じた。子供たちがどこでこだわっているかを日々の生活の中で見逃さないようにしたいし、道徳の授業においても、価値のフィルターから子供たちのこだわりを見直したときに、自分とつながって深まっていく部分が見つけられるところが道徳の楽しいところなのかなと感じている。(豊野西小 本間大貴先生)
短時間の語り合いの中で、道徳教育の鍵として浮かび上がってきたのは、やはり「対話」でした。昨今、社会生活全体の中でその存在感や期待は高まり、実感できる豊かさを満たすことにおいて今後強く求められていくものだとも感じています。学校教育においても、対話の可能性について触れる機会は多くなり、今では学習活動の中心に位置づきつつあるように感じています。しかし私たちは、対話を手段としながらも、その可能性に委ね、もたらされる効果をただ期待するだけでなく、それによって何を実現しようとしているのかを見失なってはなりません。
ある授業で、前時欠席したA生が「僕はここまでしか考えられていないけれども、みんなの考えを聞かせてほしい」と、友の考えを傾聴する姿勢を見せました。B生はA生の問いかけに戸惑いながら「私はえっと…、」と、まだ考えが曖昧な様子で少しずつ語り始めました。A生が「それはこういう意味?」とさらにB生に迫ると、A生は「あっ…そうか、こういうことかもしれない」と、迷いが晴れたような眼差しに変わりました。
A生は、自分の現在地を自覚して友の考えを吸収して自分の考えの行き先を探り出そうとし、B生はA生に迫られる中で自分の考えている曖昧なものに目を凝らし、言葉で出力したことで自己の考えが鮮明になっていきました。二人はそこから一度自分一人で深く考えていました。
対話は、させられるものではなく、発生するものであってこそ主体的なものになると考えられていますが、授業の際には教師の導きや誘いによるものが大きいのも現実です。先の授業も教師の導きがもたらした対話ではありましたが、A生もB生も対話を助けに自己と向き合うことで、それぞれの解に向かっていました。二人の異なる解は、A生は対話から求め、B生は対話によってもたらされたもので、それぞれの現在地において最も重要で尊い解となったと同時に、対話を通して解を求め得た経験は、主人公として社会に生きる上で尊い体験でもあったはずです。
心が迷ったとき、他者に問いかけたり、自分の気持ちを言葉にしてみたりしながら、最後は自己に問いかけて答えを見つけ続けていく。そのための対話は、何が起きるかわからない怖さも秘めながら、自己の答えに自ら手を伸ばすための確かな助けになるものだと実感しています。