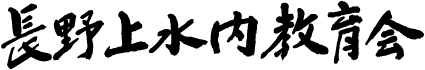【この投稿は・・・】
1月15日付で「データベース v 2.00」のチラシが出ます。新版の「メイキングVTR」的なブログを連作でお届けします。
「v 2.00」からは一般公開が始まります。移転前のデータベースはブラックボックスで、委員でさえ全データを一括して見ることは困難でした。2021年度に教育会サーバに移転すると作業環境が向上し、全データの「出自」を洗い出す作業が少しずつ進みました。それらの(その時点では何も生まない)細かな作業の全てが、今回の一般公開に結びついています。今回は、そんな多くの委員たちの知られざる努力へのリスペクトを込めた、ココだけで読める裏話、題して「未来への遺産」編です。堅い話ではありませんが、少し長いので、お時間のあるときにでも・・・
【初めて明かされる “初代” 誕生と道のり】
今だから言えますが、サーバ移転時のコンセプトは、「どんな働きをしてるかわからないデータも多いけど、とにかく何一つ失わないように引っ越せ」でした。アバウトにもほどがある(汗)。2021年からの歩みを医療に例えると、医師が自分の体をCTや超音波で検査しながら手術しているような三年間でした。
フリーワード検索、地区による絞り込み、時代の区分などは、私たち自身の「検査手法」にもなります。見方を変えれば、自分の体で実験しながら検査機器を開発している、とも言えるでしょう。新しい検査機器をつくっては自分の健康診断を繰り返し、精度を向上させてきたのです。その1つの成果として、つい先日、18点の航空写真の出典を特定し、撮影者に公開許諾を得ることができました。最後の「診断」は筆者が下しましたが、とうてい一人でどうにかできるものではありません。
【答えに導く最大のチカラ】
この「救出」は「出典不明」データの整理作業の一環です。84点ある出典不明データは、いま最も「一般公開」から遠いもので、将来は破棄される運命です。その中の航空写真18点を集めてみると「画像の質(画質、色調、撮り方)」や投稿者の「タイトルの語感」に統一感がありました。なんだか推理小説みたいですが実話ですよ(笑)
ここまでサラッと書きましたが、1,700点余のデータを全部見て、一つずつ「航空写真」という属性を入力したのも、全てのデータの出典を細かな手がかりから洗い出した上で、「これだけは降参」という84点を絞り込んだのも、全て歴代の委員です。これらの膨大な「カルテ」こそ本当の宝で、これがバックにあるから適切な検索ができるのです。ちなみに2025年1月13日現在、航空写真は110点ありますが、今なら3秒でわかります。
【ありがたい協力】
妙に統一感のある18枚の航空写真は、筆者に「どこかで見た記憶」を呼び起こします。「これ、教育会館の玄関の写真・・・確かアレは・・・」大急ぎで手元の「社会科資料集(教育会編)」を開きます。壁の写真提供者が「資料集」と同じだったからです。すると何枚か「同じ」と言える写真がありました。となれば、問題は撮影時期です。戸隠はあるのに中条や信濃町はない・・・豊野北部の五岳道路が未着工・・・写真から読み取れる事実は、2005年度末~2009年度末の状況を示唆しています。事務局にあるこの期間の資料集と対照すると、ビンゴ! 2007年度版資料集と完全に一致しました。
すぐさま事務局に連絡すると、撮影元の業者さんが一般公開を快諾してくださり、加えて最新の写真セットもご提供くださることに・・・、こうして、まもなく最新と20年前の航空写真とをデータベース上で比べることができるようになる(作業中)のです。
【広がる支援の輪】
すでに出典特定済みのものにも、似た例があります。1988年に長野市が発行した書物からは、全くバラバラに15点の写真を借用していましたが、これらを出典元の書籍と照合しながら市の担当部局と交渉すると、正式に許諾を得てクレジット付きで公開することに同意が得られました。手続きは進行中なのでまだ反映できていませんが、元の写真集が良いモノで、追加の申請も準備していますので、明治~昭和の「公共」を知る優れた写真が一気に増量(たぶん100点以上)する予定です。
今回のバージョンからリンクで提携した「好奇心の森」さんも、長野市の文化財関連部局が四所共同で進めているものですし、このような支援の輪はこれからも拡大するでしょう。
【新しい場に立つ覚悟】
忘れてならないのは、「一般公開」によって、近隣地域の児童生徒や、全ての保護者もこのデータベースを見られるようになる・・・ということです。上水内郡の児童生徒が見られるようになったのでさえ2021年ですが、また一段ステージが上がります。ここから何が始まるか予想もつきませんが、風土や文化は行政界を超えていますから、私たちに、「少なくとも長野盆地(善光寺平)サイズの視野」と、大人も子供も対象とした「相手意識」とが不可欠になることは間違いないでしょう。
その昔、教科書もなかった時代に、仲間で集まり手作りした「教育会」の原点は、DX時代にも引き継がれようとしているのでしょう。
教材データベース委員長:遠藤公洋(小川中学校)