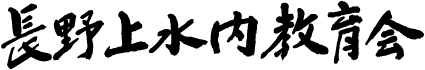【この投稿は・・・】
新稼働の「教材データベース v 2.00」に寄せる、「メイキングVTR」的なブログの2作目です。お時間のあるときにでも・・・
【はじまり】
話は、第二回委員会から始まります。今年、どんなことをしようか、という意見交換で、新しい委員さんが「個々の教材の位置を地図で示せないか・・・」と発言されたのです。筆者は内心「ついに来たか・・・」と思いました。「ついに」とは、自分でも「いずれ必要だ」と思っていたことと、今のデータセットでは無理だとわかっていたからです。実は、提案を実現するための作業量を考えたら、今年やりたい「内部リンク」構築のためには手を出したくない作業だったのです。
【それなら、どうして今年やったのか・・・】
私たちの委員会には強力なパートナーがいます。カシヨ(株)さんのチームで、委員会の場はいつも、委員が出す要望やアイディアを彼らがシステムに落とし込み、そこで生じる課題や選択肢に委員が現場目線で回答するという「最前線」になります。
この時は、「準備ができたデータだけ地図表示できますか?」という委員長の現実的(逃げ腰とも言う)な案に、カシヨ(株)さんが「準備ができてない教材では地図のチの字も見せない」という素敵な打開策を示したので、委員長も「それなら可能な分だけやるか」という気になったのです。
それで、テスト的に始めてみたら、各データの座標同士の演算で「位置によるリンク」が作れることに気づきます。そのアイディアを、サムネイルを用いて画面に示すシステムに落とし込んだのは、もちろんカシヨ(株)さんです。そのテスト・ランの結果、地図表示システム(場所のリンク)は、今年の主要課題「内部リンク」の「もうひとつの形」だということがはっきりし、主要課題に昇格しました。こうして、新しい教材観(「場所」というストーリーで結ばれた教材群)を可視化するシステムが誕生しました。
【山間地に多い延喜式内社】
教育会事務局は「閉校していく学校の記録を残しておきたい」という願いを、おりに触れて公にしています。教育会としては自然な気持ちだと思いますが、筆者の作業では、あくまで「閉校のデータが児童生徒に役立つか」が第一です。そんな筆者の頭の中で、「学校跡」がジグソーパズルの最後のピースのようにハマった瞬間がありました。
その日は当信(たにしな/旧信州新町)の取材で、初めて同地の神社を訪れ、スギの巨木に瞠目し、「式内社はダテじゃない」と思いました。「延喜式神名帳」と通称される平安時代の神社目録があり、そこに名があるか、候補とされる神社を「式内社」と呼びます。かなり古い神社の可能性があり、地域で大切にされてきた神社です。
当信神社が鎮座するところは相当の山あいです。しかし、堂々たる、というよりあきらかに現存集落に対してオーバーサイズの神社だったので「やっぱり」と思いました。実は、長野県北部の古仏は標高700m以上にある例が多いと筆者は考えていて、どうやら式内社の分布もそれに似ているようです。現在便利な平坦地(自動車社会)ではなく、まず山麓や山間に最初の地域社会が拓かれた時代の様相を、平安まで遡る古社寺は静かに物語っているのでしょう。

【写真上】「当信神社と社叢」むやみに伐られることがない社叢には、地域の極相林としてモミの巨木(左端)もあった
【いろいろな人やモノが出会う場所で “知” が生まれる】
そこまでは比較的容易に想定できることですが、これに「学校跡」の分布が見事に重なりました。当信では、谷の向かい側の尾根に「信級小学校」跡が、これまたオーバーサイズで残っていました。そういうことか! と瞬間的に、最近歩いた式内社がフラッシュバックされます。七二会、信更、中条、小川、信州新町・・・どれも近くに意外な大きさの学校跡が残っています。
大きな集落の近くや通学に便利な道路沿いなどに学校を建てたのはごく当然なことで、ずっと昔にも同じ理由で地域の核となる古社寺がそのような場所に営まれたのでしょう。やっぱり、信州って教育県だ・・・そして、学校って地域の核の一つなんだな、と改めて思いました。
長々書いてきたようなことも、データベースv 2.00からは手に取るように可視化されます。だって、信級小跡のページを開けば右側に当信神社が自動で出るし、信更小跡を開けば清水神社(式内論社)が出るのですから。おまけに、いずれの神社の解説にも「式内社」の文字があるので、ハッシュタグを押せば登録済みの全ての式内社が一覧に・・・。
それ、贅沢すぎるだろ・・・と筆者の中の「旧世代」的感覚は叫ぶのですが、これは、AIの原理そのものです。新しいデータベースは、こういう様々な人の願いや感覚、技能や知識などが出会う場で築かれたシステムです。そして、児童生徒には、「その先」へと学びを進めてほしいと願っています。
【写真下】「信級小学校跡」1976年の閉校から50年近い歳月を経て現存する校舎と校庭。当信神社近くからも谷越しに見えた
教材データベース委員長:遠藤公洋(小川中学校)