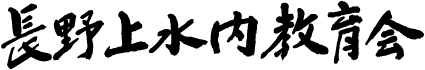◆チャットに書き込んで頂いた内容も含めて、「教育対話」に関わっての感想、ご意見を紹介します。(一部抜粋)
・子どもと向き合う中で、今の教育システムがあってないと思うことが多々あり、どういうふうに変えればいいのかのヒントがたくさん学べました。今までの教育のよさと新しい考え方や活動をうまく融合していきたいなと感じました。時間があっという間に過ぎてしまった対話でした。本当にありがとうございました。
・パネリストの先生がそれぞれの経験やお立場で感じたことを話されており、チャットの書き込みなども熱があって、道徳の多様な価値の出会う場面を参観しているようだなと感じました。主体的と自主的な目の前の子どもとどう育て合っていくかを考えさせられました。
・研修内容が盛りだくさんで、聞きたいことも盛りだくさんだったです。この研修をきっかけに、なにかこれからのあり方(学び方 教師のあり方 働き方 ライフバランス)など考え合える場ができ、また発信できると、一歩ずつでも変われるのかなと思いました。まずは足元、自校で何かできないか考えたいと思います。研修報告ありがとうございました。
・ニュージーランドの小学校では学び方を学び、その子の力に合わせた学びを学校では提供するということが印象に残りました。自分で学習の仕方を選べる環境を整えることを、少しずつ取り入れて自分もやっていきたいと思います。そして子ども一人ひとりに寄り添い、関わり合う時間を日々の生活の中で大事にしていきたいと思いました。伏木先生やパネリストの先生方のお話をお聴きしながら、自分の授業や教育観を振り返る貴重な機会になりました。ありがとうございました。
・「体育専門の教科担任が体育を行うよさ」と「担任が体育の授業を行うよさ」について、認識する機会となりました。教科担任も、学級担任くらい子どもを把握して授業を行いたいし、多数の眼で子どもを捉えたいと思いました。
・NZ研修で感じ取られたことを、各々の先生の視点で語っていただいたことがとてもよかったと思いました。今までの日本の教育の壁を皆が感じているのですが、それを打ち破っていくための切り口を参会した先生方が見つけられたように思いました。
・「”毎日が自分主体”であるから、学校が楽しみになり、不登校は少ない」というニュージーランドの小学校の様子、伏木先生のお話、視察された先生方の対話にふれて、自分の中の教育観がゆさぶられました。自校でどのような取組をしていくことが望ましいのか考えます。
・対話の中から多くのことを学ばせていただきました。知識ありきやることありきではなく、「子どもたちにとって何が必要なのか」ということを軸にして考えていく大切さに気付かせていただきました。伝統的にやっていることは何にとって大切なのかという視点に立って、今私たちが行っている教育活動や本校の教育課題をもう一度考えたいと思います。考える機会、新たな視点をいただきました。ありがとうございました。
・不登校の増加という現状から、従来の学校の在り方が限界にきていることを強く感じています。従来からの授業スタイルや教室の在り方など、古くからの常識にとらわれず、一人ひとりの子どもに目を向け、主体的で探究的な学びを重視する学校への転換の大切さを改めて実感しました。
・日本の中での教育についての様々な改革は、やはり日本の教育の決められた「枠」の中での改革であり、その「枠」を見直すには、その枠にとらわれない実践から学ぶことが重要だと感じました。本日はありがとうございました。
・外国の学校教育から学ぶ貴重な機会でした。また、参加された4名の先生方の研修姿勢が素晴らしく、これから学校現場で還元していただけるのだなと感じました。
・面白かったです。様々な面からの見方考え方があって、まとめることの難しい内容だったと思いますが、それが逆に「なるほど~」と思ったり、日本とNZとの違いだったりして、勉強になりとても充実した時間でした。当たり前と思っていることを思いこまないようにしたいと思います。
・ニュージーランドの教育、様々な立場、経験の先生方のお話をお聞きする良い機会、これまでの実践とこれからの実践をリフレクションするきっかけとなりました。「子ども中心に、シンプルかつ状況に適応しながら物事を考え、実践していくこと」が大切ではないかと感じます。
・4名の先生方や対話に参加された先生方のアドリブ力が素晴らしい! 最後に伏木先生がおっしゃっていましたが、「日本教育の良さ」も大切にしたいと感じました。
・日本とニュージーランドどちらがよいということではなく、海外の学校の様子を知ることで日本の教育のいわば当たり前になっていることを見直すよいきっかけとなりました。
・NZ教育のよさを知ることができた。外から見て日本教育の良さも聞きたかった。その視点からすると、たくさんいるALTが感じている日本教育や長野県教育のよさを聞きたいと思った。
・ニュージーランドの取組で自分のこれからの教育に関わる活動に取り入れそうなことはあるだろうかと思いながらお聞きしていました。一人一人の子どもの思い、願いを大切にして、よく聞くことは、あらためて明日からもすぐにできることだと感じたので、実践していきたいと思います。
・若い先生方のパッションを感じ、私も負けていられないと思いました。私も情熱を燃やし続け、今できることから変えていこうと思っています。
・ニュージーランドの学校の様子を知ることができて良かったです。お話にもでていましたが、そっくり真似てもうまくいかないと思います。実情に合わせて柔軟に取り入れていく事がいいと思いました。ただ、学校を変えていくきっかけ、勇気、根拠、必要を感じることができたのはとても価値があったと個人的に思います。
・一人ひとりの学び方や実態をふまえて、どのような学びを創造できるか、悩みながらも本気で取り組まれている先生方の実践から多くのことを学ばせていただきました。今の日本の教育の課題もありますが、当たり前にやっていることの中に、海外から見たら素晴らしいと感じられることがあると思います。問い続けながら、目指す方向性を共有できるように対話を続けていきたいと思います。
・一年半以上をかけて実現した ”教育対話” だけあって、良かったです。一点に収束しなくても、一論点が複線化していたので、いろいろな観点から学ぶことができました。伏木先生の公正な個別最適化のお話は、勉強になりました。また、働き方改革の観点も面白かったです。
・ニュージーランドの教育は、理想的であるかのように言われている向きもありますが、実情は格差など課題もある事が分かりました。他国と比較する事により、改めて日本の教育の良い面や課題を考えさせられました。ニュージーランド視察にはとても興味があり、次回あったら是非参加したいと思いました。
・ニュージーランドの子どもたちの様子、先生方の働き方、教育課程、先生方の対話。聞いていておもしろかったです。思わず自分も画面の向こう側ですが、考えたことを口に出してつぶやいていました。パネラーの先生方、伏木先生、ありがとうございました。
・海外の教育に触れる機会がこれまで全くなかったので、お聞きすることができ、日本の教育のこれからについて、考えていきたいと感じました。勝野先生がおっしゃっていた、「子どもは未来からのあずかりもの」という言葉を胸に、これから来るであろう変革する社会に向けて子どもとどのように学びに向かっていくべきか、私なりに考えを深めていきたいと思いました。
・学校の中だけにいると(長野県の中だけにいると)それがあたりまえになっていまいがちですが、外から眺めたり、他のやり方を体験したりすると新たな視点を得られてとてもよい機会になっていることが、パネリストの先生方の発言から感じられました。これまでの学校が全て否定されるものではないと思いますが、このままでは限界があるのも事実だと思います。今までのあたりまえを見直し、もっと子どもに寄り添った形での授業ができたらと思いました。