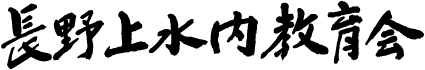第3回目のEdカフェ長水は、9月16日(月)にAカフェ、9月19日(金)にBカフェ、9月25日(木)にCカフェが行われました。今回のカフェテーマは「子どもたちの姿から学んだこと、気づかされたこと」。メインゲストとしてAカフェには、信濃教育会会長の大日方貞一先生、Bカフェには、埼玉大学教育学部教授の岩川直樹先生をお招きしました。これまでのカフェとはメンバーを変え、先生方がテーマについて語り合い、楽しくカフェタイムを過ごしました。
◇【Aカフェ】では、「子どもの姿を受け止める」をテーマに据え、それぞれの先生方が自分と子どもたちとのかかわりの中で、子どもに言われてはっと気づかされた言葉や、子どもの姿から学んだ経験などが語られました。
・「先生さ、俺たちのこと決めつけてんだよ」と言われた言葉が、今でも心に残っている。自分よがりの見方をしていたことを反省、その子のありのままの姿を見ようと気をつけている。
・タブレットを使った授業でゲームをしていた児童に「ゲームをしたいなら廊下でやって」と2回注意した。本当の理由は、黒板が見えにくく授業がよくわからなかったと判明。前の席にしたら取り組むようになった。様子や姿で判断する前に、その子の背景を理解したい。
・自分に余裕がないと、自分の方向に子どもたちをもっていってしまうことがある。小3から担任している現在5年生に、「もう、5年生だよ」と言われた。いまだに3年生のような対応をしてしまう、子どもの成長を見取ることができていない自分を反省した。
・担任をしていた頃、生徒に辛辣に批判されたことがあった。生徒たちが生活記録に様々な意見を書いてきたので、学級通信を使いながら対話を深めていったところ、子どもたちの生の声により、お互いを理解し合い、学級がまとまっていく様子があった。
・学級崩壊でクラス内に覚めた空気が漂うバツの悪さを実感したことがある。「いつまでも小学生だと思っているでしょ」と言われ、自分の至らなさを子どもから教えられた。
・不登校の子が、文化祭の有志ステージで友だちと一緒に踊っていた姿に、一人一人の子どもには自分のペースがあり、可能性があるということを教えられた。
・「私の眼の中に赤い雨が降っている」といじめられた悲しみを吐露した生徒の言葉が今も忘れられない。思うように学級経営ができなかったクラスだが、いまだに同級会によんでくれ、その度にあの時やってあげられなかったことを返してあげられるかと思う。
・小1の児童が、友だち同士うまくかかわれなくてトラブルになっていた時に、「ごめんね」と伝えるお手本を示した。そのおかげでやってしまった子は謝ることができた。たった3ヶ月の間に小1でも人間関係ができ始めていることや、その子の行動に感動した。
・子どもはありのままを出す。子どもの方が、ありのままに寄り添って行動している。
・子どもは知りたがりで、教えたがり。そんな姿をいかして、子どもが共に成長できるよう、支えていきたい。
信濃教育会会長の大日方先生は、「かつて長野市の小学校で校長をしていた時、学校不適応だった児童がいたが、地元に就職し、酒の杜氏になったと聞いた。ある時、『僕、杜氏になりました。自分が作った酒を飲んでください』と酒が送られてきた。成長して立派になった、彼のたくましい姿に、どの子にも自分を切り拓いていく力があるということを教えてもらった」と話してくださいました。
◇【Bカフェ】では、「今年の夏休み、夏休み明け」の話題を加えた、自己紹介から始まりました。埼玉大学教育学部教授の岩川先生は夏休み中、たくさん学校訪問をされたとのこと。どの学校でも先生たちは頑張っているが、時に悩み苦しんでいる。「分かち合い」が教育の根本で、大切なことを分かち合っていくのが学校。その土台は先生たち。先生たちが分かち合うことが大事であると、お話してくださいました。テーマ「子どもたちの姿から学んだこと、気づかされたこと」については、次のような意見が語られました。
・人権学習で、同じ大きさの円で描いたブドウの形に色を塗らせてみた。すると、紫色ではなく緑色に塗る子が多かった。紫色を塗った児童に「ブドウは何色?」と聞いたら、その子は周りの子が塗ったブドウを見て「黄緑」と答えた。社会的価値観の中で生きていることを感じ、子どもの見取りがまだまだ甘い自分に気づかされた。
・自分にとって昨日のことのように心にある経験がある。小4の担任をしていた時、支援級に入級しているお子さんのことを「いつもお願いね」と頼りにしていた男子児童がいた。その子がある時から学校にパタッと来なくなった。原因を聞いてみると、「頼まれることが嫌だったのにそれを誰もわかってくれなかった」と言われた。それを聞いたときに「何てことをしてしまったんだろう。つらい思いをさせてしまった」と思った。その子を頼りになるとみていたのが、今見えていることがすべてではないと思った。
・授業中、子どもの「あーそうか」に子どもと一緒に向き合うのも自分にとって勉強になる。
・子どもはへんなところに疑問をもつ。「おもしろいなー」とつぶやいたその瞬間が、教育の場面なのではないかと思う。
・探究的な学びも、自由進度学習も、教師と子どもとのかかわりが薄らぐのは違うなといつも思っている。共に大切なことに気づき、並び見が大切である。
・授業でクロムブックばかり使っていたが、「ホワイトボードで顔を寄せ合い、話し合う方がよい」と生徒に言われ、自分は形ばかりで駄目だったと思ったことがある。子どもたち同士のかかわりに、教師も一緒に入る授業のやり方を考えてみたいと思った。
・私たちの見ている子どもの姿は、その子のすべてではない、ほんの一部分なのかなと思った。
・嫌と言えないでいた子が行動で示し、それに気づいていく。人と人とのかかわりの中で、「分かち合う」。それ全部が教育であり、コミュニケーションである。
・並び見することで何かに気づいていく、子どもの視点に立って発見していくことにもなる。
◇【Cカフェ】では、自己紹介と近況報告の中で、高原学校、音楽会、周年行事、文化祭など行事の話題が多くあがり、「行事の中で子どもたちから学んだこと、気づかされたこと」から対話が始まっていきました。
・文化祭の時期になると生徒会顧問をしていた時のことを思い出す。自分は、疲れていたので片付けは適当でいいと思ってしまったが、最後まできちんと場を整える女子生徒がいた。その姿を見て衝撃を受け、「この子はどういう背景があって、こういうことができるんだろう」と思った。そういう感覚が自分の中では鈍っていると気づかされた。
・小1の担任を4回経験しているが、今年度、朝顔を育てている中でこれまで当たり前にやってきたことや、やり方がどうなのかと思うことがあり、子どもに教えてもらったと感じた。
・児童会まつりの中で、「12月といえば…クリスマス!」のようなゲームをした。小1の子が「ソビエト崩壊」と言った時、その1年生のすごさにみんなで感動した。その子のすごさをみんなで認めた大事な瞬間を見れてよかった。
・子どもってすごいなと思った瞬間がある。停電の時、「僕たちがチャイムの代わりをやっていい?」と申し出てくれた。また、20周年行事でカルタ取りをやったときに、地域のお年寄りに優しく接している姿があった。
・「それしかないわけないでしょう」(作 ヨシタケシンスケ)という絵本がある。大人はすぐに「未来はこうなる」と言うけど、子どもは簡単には選べない。大人は「どっちにする」とか、「こっちがだめならこっち」と言ってしまう。もっと子どもに任せてもいいと思った。そうすれば子どもへの声がけが変わると思う。
・飯綱登山への参加の仕方について、実際に登山はできなくてもその子ができる形で活動することを提案した。それを周りの子どもたちも認め、支え合えるのもいいのかなと思った。
・大人は子どもたちが歩んでくる道を知っているので、つい「こうしたほうがいい」と言ってしまう。進路に関しても、「今やっておかないと」と成績のことを言ってしまう。子どもとやり取りしながら、たくさん話をして探っていくことが大事だと思った。
・不登校の子と将来の話をするけど、「今この時が大事」だと思う。今のことを解決しなければいけないし、今に寄り添うことが大事だと思う。
・学校に行かないという信念で不登校であった生徒が、「将来、自分は看護士になる」と決め、自分が信じる道に進んでいったことに驚いたことがある。
・「さかなくん」の話を聞いたことがあるが、自分の好きなことを突き詰めることは大事。またその際、親が子どもを信じていることも大事である。
今回Cカフェには、信大から戸隠小へインターンシップに来ていた教育実習生が飛び入り参加。「大学の授業で『これが定義、正解』と教わったものでも、学校現場では、子どもの数だけ、さらには多様な子どもたちに対して、様々な教師の対応が求められると思った」と、感想を述べてくれました。
第3回目のEdカフェ長水は、「子どもたちの姿から学んだこと、気づかされたこと」をテーマに対話しました。子どもたちとかかわる日々の中で、子どもの言葉や姿から気づかされるたくさんのこと。自分の至らなさを痛感させられた、忘れられない子どもたちの言葉や出来事は、私たち教師にとって子どもから学んだ、子どもに教えられた大切な宝であり、教師としての自分を見つめ直し、成長させる機会であると思いました。また今回、大学生が「Edカフェ長水」に参加してくれましたが、こんな風に様々な方々と教育観について語り合う輪がさらに広がっていったら素敵だなと思っています。(文責 山下由紀子)