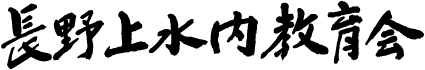10月27日(月)にオンラインで第2回研究委員長会が開催されました。まず中間報告ということで、教師力向上部からこれまでの活動の成果や今後の方向、教科研究部からこれまでの実践授業の様子や授業を通して得られた成果や今後の授業公開の予定、特別企画部から現在までの活動の進捗状況等を発表してもらいました。
委員長という大変な役を務めている先生方が「他校の学習環境づくりから多くを学んだり、児童や生徒たちとのコミュニケーションがとれることが嬉しい」「授業を公開してくださる委員の先生方が自己課題を明確にもって取り組んでいることが伝わってくる」「1つの授業をブラッシュアップして次の学校で実践することで授業に磨きがかかり、それが子どもたちの意欲的な学びの姿となって現れている」というように、委員会活動を通して感じた喜びを生き生きとした表情で語ってもらったこと、また、教師力向上部や特別企画部が昨年度までとは違う新たな取り組みに挑戦していることが感じられ、とても嬉しく感じられました。
後半は5グループに分かれ、「①現場のニーズに即した内容や今後の教育の動向を加味した、会員の必要とするテーマ別、課題別の委員会の新設・再編等をどうするか」「②委員会の構成メンバーがあまり変わらない、自己推薦の方が少なく、委員会の成立に困難が伴う現状をどうしていくか」「③日程や時間の問題があり授業公開への参加が難しい中、いかに参加者を増やし、会員全体の授業力の向上につなげていくか」という3つのテーマについて議論していただきました。
③を中心に話し合いを進めたグループのある委員長の先生から「授業をする大変さよりも子どもたちを置いて、他校に参集する大変さや苦しさはどうしても拭えない…。」という苦しい思いが語られました。委員の先生方の多くが同じ思いをもっていることでしょう。参集の負担を軽減するため、チームスに指導案を上げて委員の先生方から意見を募ったり、オンラインで授業研究会をもったりという工夫をしている委員会が増えてきてはいるものの、「どうしても実際に授業を見ることでしか感じられない子どもたちの表情の変化や醸し出すオーラ、授業をする先生の熱量がある」「委員の先生方とあえて顔を合わせることで、よいアイディアが生まれる」という声が上がりました。私たち管理職がもっと先生方の声を聞き、学校体制を工夫して多くの先生方が活動しやすく、学びやすい環境づくりをしていく必要があることを感じさせられました。
研究委員会の活動も後半となり、委員長をはじめ、委員の先生方にはこれまで以上にご苦労いただくことになります。また、教科研究部の委員の先生方にもまだまだ多くの授業公開をしていただきます。委員以外の先生方には、ぜひ積極的に公開授業に参加していただいたり、自校の委員の先生方が少しでも活動しやすいようにサポートしていただいたりしてもらえるとありがたいです。(文責:信里小学校 高橋 俊)